No.1170
11月27日、出版打ち合わせと財団の会議の間の時間を使って、アメリカ・イギリス・インド合作の冒険ファンタジー映画「落下の王国 4Kデジタルリマスター」をヒューマントラストシネマ有楽町で鑑賞。2006年の作品ですが、わたしは未見でした。劇場が満員だったのには驚きました。DVDやブルーレイを入手することは困難で、配信もされていないため、現在は「幻のカルト映画」として、とりわけアート志向のファンから熱烈に支持されてきた作品です。肝心の内容ですが、想像通りに素晴らしかったです!
ヤフーの「解説」には、こう書かれています。
「『ザ・セル』のターセム監督が製作した、美しい美術品のような感動巨編。自殺願望のあるスタントマンが幼い少女を操るために始めた虚構の物語が、やがて夢と希望を紡いでいく様子を丹念に映し出す。傷ついた青年役に『グッド・シェパード』のリー・ペイス。彼を慕う少女を演じるのは、これが映画デビュー作となるカティンカ・ウンタール。CGに頼らず、世界遺産を含む世界24か国以上で撮影された驚きの華麗な映像に息をのむ」
ヤフーの「あらすじ」は、以下の通りです。
「左腕を骨折して入院中の5歳の少女アレクサンドリア(カティンカ・ウンタール)は、脚を骨折してベッドに横たわる青年ロイ(リー・ペイス)と出会う。彼は彼女にアレキサンダー大王の物語を聞かせ、翌日も病室に来るようささやく。再びアレクサンドリアがロイのもとを訪れると、彼は総督と6人の男たちが織り成す壮大な叙事詩を語り始める」
「落下の王国」のメガホンを取ったターセム・シン監督は、1961年5月26日生まれの64歳。インドのパンジャーブ州ジャランダル出身。インドの名門校ビショップ・コットン・ボーイズ・スクールを卒業後、渡米し、ハーバード大学でビジネスを、カリフォルニアのアートセンター・カレッジ・オブ・デザインで映像制作を学びました。大学卒業後からMV監督の仕事に就き、ロックバンド「R.E.M.」の楽曲「Losing My Religion」 のMVでMTVビデオ・ミュージック・アワードの最優秀ビデオ賞など6部門を受賞。並行してCM監督としても活躍しました。長編映画監督としてのデビュー作は、視覚技術を駆使したSFスリラー「ザ・セル」(2000年)です。
「ザ・セル」の舞台は、先進的な医療施設キャンベルセンターです。そこ働く小児精神科医のキャサリン・ディーン(ジェニファー・ロペス)は、昏睡状態の少年エドワード・べインズ(コルトン・ジェームズ)の内面世界に特殊な機器を使って入り込み、内なる彼とやりとりしながら意識の回復を目指す治療に携わっていました。結果は芳しくなく、キャサリンは自分の内面にエドワードを招き入れる方法を考慮していましたが、それは未知の領域でリスクがありました。そんなある日、昏睡状態の連続殺人犯カール・スターガー(ヴィンセント・ドノフリオ)がセンターに運び込まれます。彼に誘拐された女性がタイマー仕掛けで溺死させられる危機にあるため、彼女が閉じ込められている場所をカールの内面から聞き出そうというのでした。
「落下の王国」は、ターセム・シン監督にとって長編映画2作目となります。1915年のロサンゼルス。無声映画のスタントマンだったロイ・ウォーカーは、撮影中に大怪我を負い半身不随となった上に、恋人を主演俳優に奪われ、入院先の病院で自暴自棄になっていました。そんなとき彼の病室に現れたのは、家族を手伝ってオレンジの収穫をしている際に、木から落ちて腕を骨折して入院していた移民の少女、アレクサンドリアでした。ロイは、動けない自分に代わって自殺するための薬を盗んで来させようと思い、アレクサンドリアに取り入るために、作り話を聞かせ始めます。それは1人の悪者のせいで愛する者や誇りを失い、深い闇に落ちた6人の勇者達が、力を合わせて悪者に立ち向かう愛と復讐の物語でした。本作のヒロインであるエヴリンを演じたジャスティン・ワデルが最高に美しかったです。惚れました!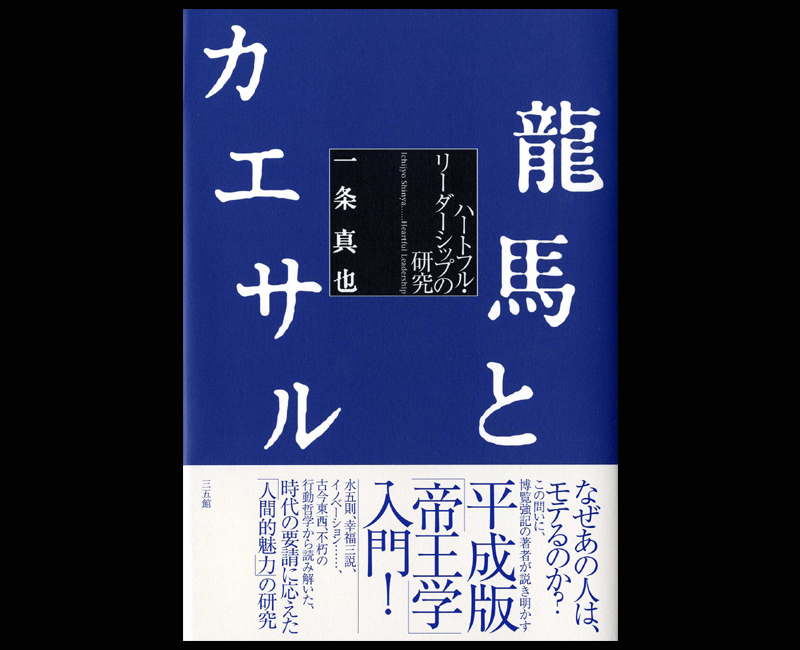
『龍馬とカエサル』(三五館)
少女アレクサンドリアに対してロィが語った物語の冒頭に、かつてわたしが『龍馬とカエサル』(三五館)で紹介したアレクサンダー大王のエピソードが登場して驚きました。アレクサンダーは1600キロに近いゲドロシア砂漠を越えるのに60日間を費やしましたが、それは軍隊の世界史に残るほど恐ろしい苦難でした。暑い10月の太陽に照らされながら、マケドニアの兵士と将兵が砂漠を進むにつれて、ひどい惨劇が繰り広げられました。蹉跌のない馬などの駄獣の多くは、餌も水もないまま砂漠に倒れました。その死んだ動物を兵士は切り刻んで食べました。落伍者はさらに困難な事態に直面します。本隊の兵士が食料を手にした頃、彼らのために残されたものは僅かでしかなかったからです。
何人かの兵士がなけなしの水を兜に入れて、喉をうるおすようにとアレクサンダーのところに持ってきました。兵士たちは、アレクサンダーが楽をするどころか、軍勢の先頭に立って馬にも乗らずに砂地を徒歩で進んでいることを知っていました。しかし、その貴重なもらった水をアレクサンダーは砂漠に撒いたのです。そして、「君たちのおかげで喉の渇きは癒えた」と言ったのでした。兵士たち全員が飲めないのであれば、水を飲むつもりはなかったのです。その後、軍全体がすっかり元気を取り戻し、彼が捨てた水がすべての人の喉の渇きを癒したと思われるほどだったとか。いくらリーダーとはいえ、極限状態で水を捨てるなど、とてもできることではありません。アレクサンダーは「王の中の王」でした。
『愛する人を亡くした人へ』 (PHP文庫)
ロイは動けない自分に代わって、自殺するための薬を薬剤室から持って来させようと、少女に思いつきの冒険物語を紡ぎ聞かせ始めていきます。しかし、それはいつしか少女に希望を与え、やがて自分自身をも救う壮大な物語へと広がっていきます。まさに物語がケアの力を発揮したわけですが、わたしは拙著『愛する人を亡くした人へ』 (現代書林・PHP文庫)の中で指摘した葬儀の機能について思い出しました。愛する人を失った遺族の心は不安定に揺れ動いています。しかし、そこに儀式というしっかりした「かたち」のあるものが押し当てられると、不安が癒されていきます。心が動揺していて矛盾を抱えているとき、この心に儀式のようなきちんとまとまった「かたち」を与えないと、人間の心にはいつまでたっても不安や執着が残るのです。
愛する者との死別による不安や執着は、残された人の精神を壊しかねない、非常に危険な力を持っています。この危険な時期を乗り越えるためには、動揺して不安を抱え込んでいる心に、ひとつの「かたち」を与えることが求められます。まさに、葬儀を行なう最大の意味はここにあります。では、この儀式という「かたち」はどのようにできているのでしょうか。それは、「ドラマ」や「演劇」にとても似ています。死別によって動揺している人間の心を安定させるためには、死者がこの世から離れていくことをくっきりとしたドラマにして見せなければなりません。ドラマによって「かたち」が与えられると、心はその「かたち」に収まっていきます。すると、どんな悲しいことでも乗り越えていけます。それは、いわば「物語」の力だと言えるでしょう。
わたしたちは、毎日のように受け入れがたい現実と向き合います。そのとき、物語の力を借りて、自分の心のかたちに合わせて現実を転換しているのかもしれません。つまり、物語というものがあれば、人間の心はある程度は安定するものなのです。逆に、どんな物語にも収まらないような不安を抱えていると、心はいつもぐらぐらと揺れ動いて、愛する人の死をいつまでも引きずらなければなりません。仏教やキリスト教などの宗教は、大きな物語であると言えます。「人間が宗教に頼るのは、安心して死にたいからだ」と断言する人もいますが、たしかに強い信仰心の持ち主にとって、死の不安は小さいでしょう。中には、宗教を迷信として嫌う人もいます。面白いのは、そういった人に限って、幽霊話などの小さな物語を信じるケースが多いことです。いずれにしろ、人間は不安定な心を安定させるために物語を必要とするのです。
ロイの語る物語は、巨悪の総督オウディアスへの復讐を誓う個性豊かな5人の勇者にまつわるものでした。3人目の勇者であるルイジは、渋い口髭に葉巻、片手に拳銃という風貌に加え、「爆発物の専門家」という異色のスキルを持っています。しかしその能力ゆえに総督オウディアスから危険視された彼は、周囲から断絶させられ、孤立へと追い込まれてしまうのでした。敵の非情な仕打ちに、ルイジは烈火のごとく怒りを爆発させます。特異な魅力を持つ勇者たちの中でも、ひときわ強烈な存在感と戦闘力を誇るルイジ。壮大な風景が広がる劇中世界で、彼が放つ圧巻の爆破シーンは圧巻でした。ロイの想像力が生み出した勇者たちが命を落とすたび、アレクサンドラは涙を流しながら「だめ、殺さないで!」「死なせないで!」と懇願するのでした。
「落下の王国」という奇妙な映画を作るにあたって、ターセム監督は、ザコ・ヘスキジャ監督のブルガリア映画「Yo Ho Ho」(1981年)から着想を得たといいます。同作は、今でも日本国内には配給されていない「病院」を舞台にしたヒューマン・ドラマです。「落下の王国」では、幼い少女とスタントマンの青年が主な主人公でしたが、「Yo Ho Ho」の設定は人生に絶望した男優と骨折して入院中の10才の少年との交流を描いています。両作品の設定は微妙に違っていますが、共通しているのは「生」に絶望した入院患者の男が、少年や少女を通して再び生きる意味を見出そうとする姿です。おそらく、ターセム監督も「Yo Ho Ho」のそこに感銘とインスピレーションを受けたのでしょう。
本作を下敷きにして作られた「落下の王国」はじつに構想26年、13の世界遺産、24ヶ国以上でロケーション撮影され期間4年を費やされました。ブログ「きっと、うまくいく」で紹介した2009年のインド映画の大ヒット作のラストシーンの舞台にもなったインド最北部のパンゴン湾をはじめ、タージ・マハル、ファテブル・シークリー、アーグラ城、アンコールワット、万里の長城、トワイフェルフォンテイン、ピラミッド、エッフェル塔......次から次に万華鏡のようにスクリーンに登場する世界遺産に魅了されました。第38回カンヌ国際映画祭で芸術貢献賞、第65回アカデミー賞で衣装デザイン賞を受賞している石岡瑛子が衣裳デザインを担当。提供者としてスパイク・ジョーンズ、デヴィッド・フィンチャーがクレジットされています。
「落下の王国」のテーマ曲として用いられているのはベートーヴェンの「交響曲第7番」の第二楽章です。"楽聖"ベートーヴェンの9つの交響曲の中の番7目の交響曲が「交響曲第7番」。第3番「英雄」、第5番「運命」、第6番「田園」、そして「交響曲第9番(合唱付き)」などと並ぶ代表作であり、かつ人気曲です。重厚で切ないそのメロディは多くの映画でも使用されました。「落下の王国」では冒頭と終わりで流れました。映画そのものは希望をもって終わった印象でしたが、この曲が流れるとどこか喪失感がありました。「目の前の問題は解決したけれど、悲しみは消えず」といったところでしょうか。まさに、グリーフケアのための永遠の名曲だと思います。最後に、「落下の王国」という伝説のカルト映画を劇場で観ることができたのは得難い経験でした。ただし4K上映ではなく、2Kでの鑑賞だったのが残念ではありましたが......。




