No.0333
映画「ウィンストン・チャーチル/ヒトラーから世界を救った男」のレイトショーを日比谷シャンテで観ました。
ヤフー映画の「解説」には以下のように書かれています。
「『つぐない』などのジョー・ライト監督と、『裏切りのサーカス』などのゲイリー・オールドマンが組んだ歴史ドラマ。第2次世界大戦下のヨーロッパを舞台に、苦渋の選択を迫られるウィンストン・チャーチルの英国首相就任からダンケルクの戦いまでの4週間を映し出す。チャーチルの妻を『イングリッシュ・ペイシェント』などのクリスティン・スコット・トーマスが演じるほか、リリー・ジェームズ、ベン・メンデルソーンらが共演。『博士と彼女のセオリー』などのアンソニー・マクカーテンが脚本を担当している」
また、ヤフー映画の「あらすじ」には以下のように書かれています。
「第2次世界大戦勃発後、ナチスドイツの勢いはとどまることを知らず、フランスの陥落も近いとうわさされる中、英国にもドイツ軍侵攻の危機が迫っていた。ダンケルクで連合軍が苦戦を強いられている最中に、英国首相に着任したばかりのウィンストン・チャーチル(ゲイリー・オールドマン)がヨーロッパの命運を握ることになる。彼はヒトラーとの和平か徹底抗戦かという難問を突き付けられ......」
ブログ「全互協九州ブロック総会」で紹介した懇親会で、業界の大先輩であるラックの柴山社長からススメられた作品です。柴山社長は「あれほど感動した映画はない。ヨーロッパに行く前にぜひ観ておくといいですよ」と言われていました。その言葉に導かれた観たわけですが、わたしも非常に感動しました。リーダーシップの本質を見事にとらえた映画だと思いました。
この映画の原題は"Darkest Hour"です。「最も暗い時間」という意味ですが、それはヨーロッパがアドルフ・ヒトラーに蹂躙された時間のことでした。邦題には「ヒトラーから世界を救った男」とありますが、登場するのはチャーチルばかりで、ヒトラーはまったく登場しません。
首相に就任したばかりのウィンストン・チャーチルを主人公に、第二次世界大戦中の激動の時代を描いた作品です。わたしは、ヒトラーもチャーチルも世界史上に残る重要人物であると思っています。まさに2人は「鷲とライオン」と呼ぶべき宿命のライバルでした。
「ウィンストン・チャーチル/ヒトラーから世界を救った男」には第2次世界大戦期の英国国王であったジョージ5世が登場します。彼は首相であるチャーチルと2人きりで会食したり、チャーチルの自宅を突然訪問して意見を述べたりするのですが、こういった場面にはちょっと驚きました。さらには、ジョージ5世はチャーチルに対して「われわれの友情」といった言葉さえ使っています。日本では考えられないことですね。
ブログ『街場の天皇論』で紹介した本で、思想家の内田樹氏は「『今』の天皇制システムの存在は政権の暴走を抑止し、国民を統合する貴重な機能を果たしている」と述べていますが、イギリスの場合はもっとダイレクトに国王が首相に意見を述べていたのですね。それも戦時中の日本で昭和天皇が東條首相に物申すといった感じではなく、もっとフランクな印象です。ここは、「さすがはイギリス!」と言うべきなのでしょうか。
ジョージ5世といえば、一条真也の映画館「英国王のスピーチ」で紹介した名画の主人公です。「英国王のスピーチ」は第83回アカデミー賞で作品賞、脚本賞、監督賞、主演男優賞の4冠に輝きました。戦時にジョージ5世が国民を演説で鼓舞するため、言語聴覚士のライオネル・ローグとともに吃音の克服に挑むという内容です。この時期はマイクの性能が進み、ヒトラーの台頭を後押しする役目を果たすことになりました。さらには、ラジオという最新メディアが出現しました。
「英国王のスピーチ」の最後でスピーチ会場に出向くジョージ5世に対して、ウィンストン・チャーチルが「じつは、わたしも言語障害に悩まされました。でも、最後は自分で乗り越えました」とささやきます。雄弁家として知られるチャーチルの意外な過去を知った国王は一瞬驚きつつも、「ありがとう」と感謝の言葉を述べます。極度の緊張状態にあった場面で、チャーチルの一言によって、彼の心はどれだけ慰められたでしょう! それだけ人の心に影響を与えることのできる一言を発したという事実だけでも、チャーチルは真の「言葉の天才」だったと思います。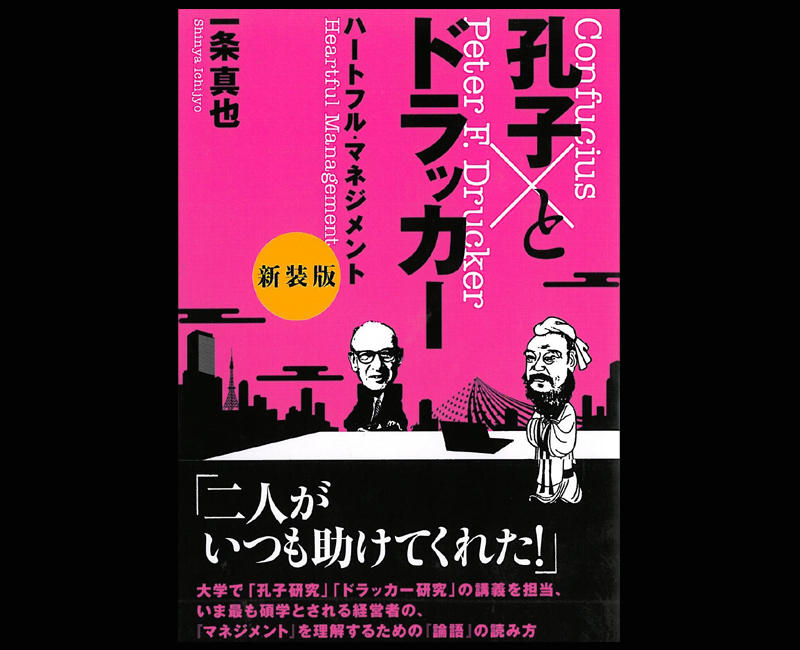
『孔子とドラッカー新装版』(三五館)
ウィンストン・チャーチルは名演説家として知られましたが、「人に与えられたあらゆる能力のなかで、話術ほど重要な能力はない」と言いました。欧米人のあいだでは「スピーチは命である」という考え方が徹底しています。
拙著『孔子とドラッカー新装版』(三五館)の「言のマネジメント」にも書きましたが、スピーチをするときに一番大切なのは、最初の10秒間だといいます。なぜなら、その10秒間で勝負がついてしまうからです。気が散っている人や、興味を示さない人の心に食い込むのは、このときです。相手を集中させ、興味を引くのは、このときしかないのです。
そもそも、政治の世界において大切なことは「何を語るか」ではなく、「誰が語るか」です。そして、それは政治の世界だけではなく、経営の世界においても同じだと思います。経営者にとっての究極の役割とは、力に満ちた言葉、すなわち「言霊」を語ることだと思います。社員の心を励ます言葉。マネジャーの胸を打つ言葉。経営幹部の腹に響く言葉。顧客の気持ちを惹きつける言葉。そうした言霊の数々を語ることこそ、経営者の役割ではないでしょうか。
「言霊」について考えた場合、決してリーダーが口にしてはならない言葉があります。「吾れ言を知る」と言った孟子は、その「言」を4つ挙げています。
1つは、詖(ひ)辞。偏った言葉。概念的・論理的に自分の都合のいいようにつける理屈。2つ目は、淫辞。淫は物事に執念深く耽溺することで、何でもかんでも理屈をつけて押し通そうとすること。3つ目は、邪辞。よこしまな言葉、よこしまな心からつける理屈。4つ目は、遁辞。逃げ口上のことです。つまり、これら4つの言葉は、リーダーとして決して言ってはならない言葉なのです。
では、リーダーは何を言うべきなのでしょうか。それは、真実です。リーダーは第一線に出て、部下たちが間違った情報に引きずられないように、真実を語らなければなりません。部下たちに適切な情報を与えないでおくと、リーダーが望むのとは正反対の方向へ彼らを導くことにもなります。そして説得力のあるメッセージは、リーダーへの信頼の上に築かれます。信頼はリーダーに無条件に与えられるわけではありません。それはリーダーが自ら勝ち取るものであり、頭を使い、心を込めて、語りかけ、実行してみせることによって手に入れるものなのです。
「ウィンストン・チャーチル/ヒトラーから世界を救った男」は、どちらかというと地味な映画です。しかし、これほど教養的な映画はないと思いました。チャーチルは演説を行うにあたって、キケロやホラティウスといった古代ローマの賢人や詩人の言葉を駆使するのですが、まさに教養としてのリベラル・アーツは古代ローマで生まれたものなのです。チャーチルは真の教養人だったのでしょう。また、チャーチルが地下鉄に乗って英国民の声を直に聴いたとき、ある黒人が「先祖や神々のために」ナチスに負けないように闘おうと言いました。その言葉に触れたチャーチルは思わず涙ぐむのですが、このシーンを観て、わたしも涙が出てきました。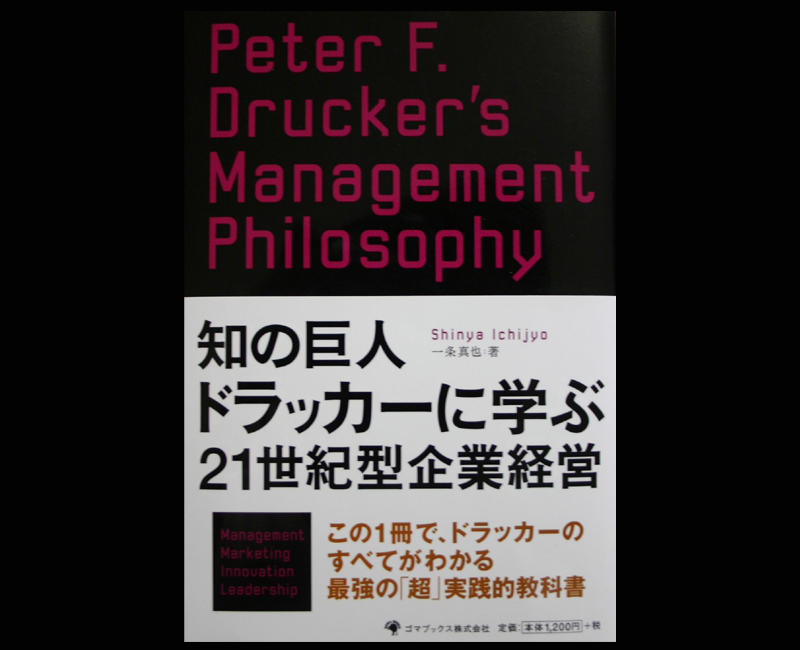
『知の巨人ドラッカーに学ぶ21世紀型企業経営』(ゴマブックス)
2006年3月に上梓した『知の巨人ドラッカーに学ぶ21世紀型企業経営』(ゴマブックス)において、わたしは、ドラッカーが常々、「20世紀最高のリーダーはチャーチルだった」と語っていたことを紹介しました。
リーダーたる者は、組織に献身しつつも個たりえなければなりません。そのとき仕事もうまくいくのです。また、自らを仕事の外に置かなければなりません。さもなければ、大義のためとして自らのために仕事をすることになります。自己中心的となり、虚栄のとりことなります。とりわけ、焼きもちを焼くようになるのです。チャーチルの強みは、最後まで後進の政治家を育て後押ししたことにあったと、ドラッカーは評価しました。
ドラッカーの処女作である『「経済人」の終わり』もチャーチルに言及しており、敬意をもって扱っていました。彼自身、当時は閑職にあったチャーチルがリーダーシップをとることを願っていたことが明らかです。同書が出版された1939年には、チャーチルは可能性の1つにすぎませんでした。70歳に近づきつつある無力な老人でした。熱っぽい口調にもかかわらず、あるいはそれゆえに聞き手を退屈させる現代の予言者でした。野にあっては偉大かもしれませんが、二度破れた敗者にすぎなかったのです。
しかし翌40年、チェンバリンがダンケルク撤退とフランス陥落によりイギリス首相の座を降り、チャーチルが登場した。これこそ、ドラッカーが望み、祈った道義的政治的価値の意味を確認するものでした。だが、1939年当時、人々にできたのは望み祈ることだけでした。1930年代の現実は、完全ともいうべきリーダーシップの欠如でした。政治の舞台に役者は大勢いました。あれほど政治家が熱心に動き回った時代はありませんでした。その多くが真面目でした。大いに能力のある者もいました。だが、ヒトラーとスターリンという2人の闇の帝王以外は、悲しいほどに小粒でした。並でさえありませんでした。全体主義の邪悪な力との戦いにおけるリーダーとしてのチャーチルの登場は決定的でした。まさに運命の境目だったのです。
ドラッカーは、「チャーチルの重要性についてはまだまだ認識不足である」と述べています。ダンケルク撤退とフランス陥落の後、チャーチルが自由世界のリーダーの地位につくまでは、ヒトラーが無謬の存在として闊歩していました。しかしチャーチルが現われるや、ヒトラーの命運も断たれました。万事にタイミングを失い、敵の動きを予期するという神秘的な力を失いました。1930年代髄一の緻密家も、40年代に入ってからは無謀な賭博師にすぎなくなったのでした。
今日では、もしチャーチルがいなければ、アメリカもナチスの支配に対し手を出さずに終わったかもしれないことを実感するのは難しいでしょう。まさにチャーチルが与えてくれたものこそ、ヨーロッパが必要とするものでした。ドラッカーは、それを「道義への権威であり、価値への献身であり、行動への信奉だった」と、『「経済人」の終わり』1969年版「序文」に書きました。





