No.348
6月9日、皇太子さま、雅子さまの東宮ご夫妻は銀婚式(ご結婚25周年)を迎えられました。心よりお祝いを申し上げます。ご夫妻は、いよいよ来年5月から新しい天皇・皇后になられるわけですが、今上天皇と皇后さまは最近、「羊と鋼の森」という日本映画を御覧になりました。東宮ご夫妻の銀婚式という晴れの日に、わたしも鑑賞いたしました。
ヤフー映画の「解説」には、以下のように書かれています。
「第13回本屋大賞に輝いた宮下奈都の小説を実写映画化。ピアノの調律のとりこになった一人の青年が調律師を志し、さまざまな人々とのすそ交流や、挫折を経験しながら成長していくさまを描く。主人公・外村を『四月は君の嘘』などの山崎賢人、外村の人生に大きく関わる調律師・板鳥をテレビドラマ「就活家族 ~きっと、うまくいく~」などの三浦友和が演じる。『orange-オレンジ-』で山崎と組んだ橋本光二郎がメガホンを取り、『高台家の人々』などの金子ありさが脚本を担当」
また、ヤフー映画の「あらすじ」には、以下のように書かれています。
「北海道育ちの外村直樹(山崎賢人)は、高校でピアノの調律師・板鳥宗一郎(三浦友和)と出会い、板鳥の調律したピアノの音色がきっかけで調律師を目指すことに。やがて板鳥のいる楽器店で調律師として働き始め、先輩に同行した仕事先で高校生の姉妹ピアニスト和音と由仁に出会う」
この映画の原作は、一条真也の読書館『羊と鋼の森』で紹介した小説です。それにしても『羊と鋼の森』とは不思議なタイトルですが、羊とは「ピアノの弦を叩くハンマーに付いている羊毛を圧縮したフェルト」、鋼とは「ピアノの弦」、そして森とは「ピアノの材質の木材」を表します。羊のハンマーが鋼の弦をたたくことによって、聴く者を音楽の森に誘うという意味もあり、もう書名からしてこの上なく文学的ですね。
原作小説を読み終えて思ったことは、「この作家は本当に小説を書くことが好きなのだな」ということでした。良い意味で文学少女がそのまま大人になったようなピュアな心を感じました。冒頭の「森の匂いがした。秋の、夜に近い時間の森。風が木々を揺らし、ざわざわと葉の鳴る音がする。夜になりかける時間の、森の匂い。」という一文からも、作者の小説への愛情がひしひしと伝わってきます。
『羊と鋼の森』に話を戻しましょう。この小説を読んで、ピアノに対する見方が変わりました。もちろん昔から自宅にはピアノが置かれていたわけですが、演奏の心得のないわたしにとっては単に大きな家具でしかありません。しかし、この小説にはピアノが以下のように表現されているのです。
「ピアノは一台ずつ顔のある個々の独立した楽器だけれど、大本のところでつながっている。たとえばラジオのように。どこかの局が電波に乗せて送った言葉や音楽を、個々のアンテナがつかまえる。同じように、この世界にはありとあらゆるところに音楽が溶けていて、個々のピアノがそれを形にする。ピアノができるだけ美しく音楽を形にできるよう、僕たちはいる。弦の張りを調節し、ハンマーを整え、波の形が一定になるよう、ピアノがすべての音楽とつながれるよう、調律する」
(『羊と鋼の森』p.22)
ピアノがあれば、そしてピアノを弾けば、いつでも世界とつながることができるなんて、なんて素敵なことでしょうか。その調律という作業も奥深いわけですが、外村は「どのような音を目指せばいいのか」について悩みます、そんなとき、外村がこの道に入るきっかけとなった天才調律師の板鳥は、「明るく静かに澄んで懐かしい文体、少しは甘えているようでありながら、きびしく深いものを湛えている文体、夢のように美しいが現実のようにたしかな文体」という言葉を紹介します。小説家の原民喜の言葉ですが、おそらくは作者の宮下氏の座右の銘なのではないかと思います。
映画「羊と鋼の森」では、鈴木亮平演じる先輩調律師の柳と山崎賢人演じる主人公の外村がいろんなピアノの音を整えていきます。それぞれのピアノにはさまざまな持ち主がいて、彼らはさまざまな人生を背負っています。鈴木亮平がピアノの調律師を演じると知ったとき、最初は違和感をおぼえたのですが、映画では自然に演じられていました。西郷隆盛からピアノの調律師までを演じるなんて、役柄の広い俳優さんだと思います。
それから、主役の山崎賢人も良かったです。これまで多くの少女漫画が原作のスイーツ映画に出演し、「ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない 第一章」(2017年)の東方仗助役、「斉木楠雄のΨ難」(2017年)の斉木楠雄役など、最近は異色の役も目立ちましたが、ようやく山崎賢人らしい役にめぐりあえたという感じでした。北海道の山林で育った純粋で繊細な外村青年のキャラクターを見事に演じていましたね。彼は少女漫画に登場する王子様のような、あるいは昭和のアイドル歌手のような顔をしているのですが、その雰囲気は落ち着いていて上品でした。
外村の先輩の柳ですが、繊細な神経の持ち主で、不自然なものを見ると気分が悪くなるような人物でした。たとえば、公衆電話は目立つように不自然な黄緑色になっていますが、そういうものが目に入ると気分が悪くなります。派手な看板なども憎んでいて、「世界の敵」だと言っていました。気分が悪くなったとき、彼はメトロノームで救われました。ねじまき式のメトロノームのカチカチカチカチという音を聴いているうちに落ち着くことを発見したのです。原作者の宮下氏はメトロノームのことを「何かに縋って、それを杖にして立ち上がること。世界を秩序立ててくれるもの。それがあるから生きられる、それがないと生きられない、というようなもの」と表現していますが、これは「儀式」そのものであると、わたしは思いました。儀式とは何よりも世界に秩序を与えるものです。それは、時間と空間に秩序を与え、社会に秩序を与え、そして人間の心のエネルギーに秩序を与えます。
一条真也の読書館『言語としての儀礼』で紹介した本で、著者であるイギリスの牧師で神学者のロジャー・グレンジャーは、儀礼の本質を「人類全体の初原状態を一時的に再現」することにあると述べています。
ピアノの調律というのも「初原状態の再現」にほかなりません。さまざまな原因から狂った音を初原状態に戻すという「初期設定」を行うのです。しかし、ピアノの調律は「初期設定」だけでは不十分です。顧客の「これからは、もっと明るい音にしたい」といった要望に応える、いわば「アップデート」も求められます。これは、儀礼の場合もまったく同じことです。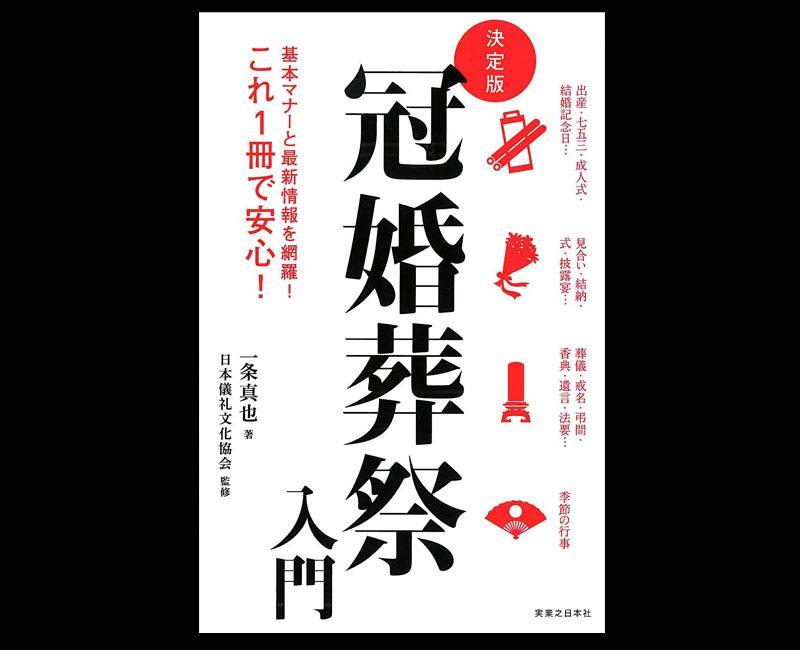
『決定版 冠婚葬祭入門』(実業之日本社)
拙著『決定版 冠婚葬祭入門』(実業之日本社)では、こう書きました。
「冠婚葬祭のルールは変わりませんが、マナーは時代によって変化していきます。最近、情報機器の世界では『アップデート』という言葉をよく聞きます。アップデートによって新しい機能が追加されたり、不具合が解消されたりするわけです。冠婚葬祭にもアップデートが求められます。基本となるルールが『初期設定』なら、マナーは『アップデート』です。本書は、現代日本の冠婚葬祭における『初期設定』と『アップデート』の両方がわかる解説書だと言えるでしょう」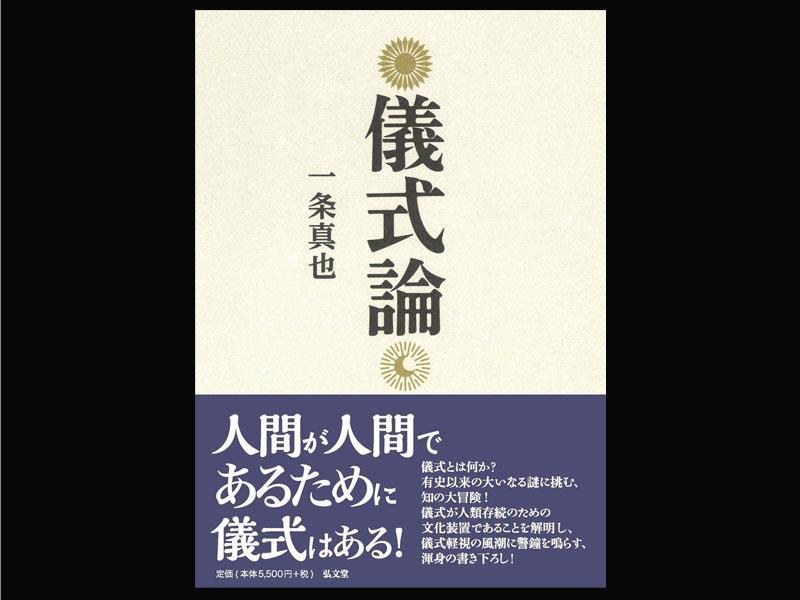
『儀式論』(弘文堂)
拙著『儀式論』(弘文堂)の第6章「芸術と儀式」にも詳しく書いたように、もともと儀式と音楽は分かちがたく結びついていました。そのことを最初に指摘した人物こそ、儒教の開祖である孔子です。孔子は、儀礼と音楽とを合わせて「礼楽」という言葉を使いました。『礼記』では「礼楽」について、「楽は同じくすることをなし、礼は異にすることをなす同じければすなはちあひ親しみ、異なるときはすなはちあひ敬す」と述べられています。その意味は、「音楽というものは、いろいろな階級や立場の異なりを超えて、人々の心をひとつにするものである。儀礼というものは、乱れる人間関係にけじめを与えるために、おのおのに立場の異なりをはっきりさせるものである。楽しみをともにするときはおのおのあい親しみ、おのおのが自己の位置と他人の立場を意識するときは、相手の立場や意見を尊重する気持がおこってくる」といったところです。
映画「羊と鋼の森」にも儀式の場面が登場します。それも葬儀と結婚式という人生の二大儀式の場面です。まず、葬儀は外村の祖母の葬儀です。吉行和子が演じました。祖母が危ないという報せが入り、外村は急いで実家に戻りましたが、間に合いませんでした。家族と、数少ない親戚、それに集落の人々が集まって、山でささやかな葬儀が営まれます。それは、いわゆる「野辺の送り」と呼ばれる葬送儀礼で、葬式行列も組まれました。
この古き良き日本の葬儀のようすを見ながら、わたしは一条真也の映画館「万引き家族」で紹介した前日観た映画を連想しました。「万引き家族」にも樹木希林演じる初枝という老婆が登場しますが、彼女が亡くなっても葬儀はあげられませんでした。吉行和子にしろ、樹木希林にしろ、日本映画界を代表するベテラン女優ですが、彼女たちが演じた老女の最後の送られ方はまったく違ったものでした。
一方の結婚式のほうは、柳の結婚披露パーティーが描かれています。柳と外村がピアノの調律をした姉妹の姉である和音がピアノを弾くことになり、外村が調律をしました。
宮下氏は、この上なく幸福なようすを以下のように書いています。「若草色のドレスを来た和音が、やわらかいピアノを弾きはじめる。荘厳というよりはすがすがしくて、最初は何の曲を弾き出したのかわからなかった。結婚行進曲。しあわせなふたりを親しい人たちで讃える、祝福の曲。装飾音符を、和音はゆっくりとまるで主旋律のように弾く。夢のように美しく、現実のようにたしかに。拍手の中を、新郎新婦が笑顔で入ってくる。テーブルの間を通っていくときに、照れくさそうにこちらに会釈をした」
(『羊と鋼の森』p.236)
映画「羊と鋼の森」には、結婚披露宴のバンケットの広さ、参加者の人数、食器の音などを配慮したピアノの調律が行われる場面が登場しますが、これこそ真の芸術ではないかと思いました。ラストが幸せな結婚披露パーティーの場面で終わったことからもわかるように、この映画は優しさに満ちています。登場人物にも悪人はいません。そして、ピアノの調律師になった外村だけでなく、すべての仕事でプロを目指す若い人たちにエールを送っていると感じました。外村は、羊のハンマーが鋼の弦をたたくことによって生まれる音楽の森を歩む人生を選びました。「今日」という日が「残された人生における第一日目」という厳粛な事実に無頓着では充実した人生は望めません。ぜひ、わたしたちも自らが選んだ仕事を「天職」であると思って、自らが理想とするプロを目指し、悔いのない人生を送りたいものです。
最後に、芸術について述べたいと思います。
作家・評論家の澁澤龍彦は、「楽器について」という秀逸なエッセイにおいて、「芸術」そのものの本質を語っています。まず澁澤は、オランダの文化史家であるホイジンガの名著『ホモ・ルーデンス』を取り上げます。この本で「人間の文化は遊びとともに発達した」と主張したホイジンガは、「音楽は人間の遊戯能力の、最高の、最も純粋な表現である。そこには何ら実利的目的はない。ただ快楽、解放、歓喜、精神の昂揚が、その効果として伴っているだけである」と述べています。
これに対して澁澤は、「まことにホイジンガのいう通り、音楽ほど純粋な芸術はなく、それは私たちを日常の現実から救い上げて、一挙に天上の楽園に運んでくれるものだろう」と感想を記しています。
ヨーロッパの中世の宗教画には、かわいい天使たちが手にいろんな楽器をもって音楽を奏でている場面が描かれています。現代日本の結婚式場やチャペルのデザインなどにも、よく使われていますね。澁澤は、その天使の楽器について、さらに「天上」というキーワードを重ねて、「たしかに最高の音楽は、いわば天上的無垢、天上的浄福に自然に到達するものと言えるかもしれない。アンジェリック(天使的)という言葉は、たぶん、音楽にいちばんふさわしい言葉なのである」と述べています。英語でもフランス語でもドイツ語でも「遊ぶ」という言葉と「演奏する」という言葉は同じです。英語では「プレイ」ですが、日本語でも「遊ぶ」という表現は、古くは「神楽をすること」あるいは「音楽を奏すること」という意味に用いられました。
ここで、わたしが思い浮かべるのが、一条真也の映画館「おくりびと」で紹介した映画の主人公です。納棺師になる前の主人公はチェロ奏者でした。チェロ奏者とは音楽家であり、すなわち、芸術家です。そして、芸術の本質とは、人間の魂を天国に導くものだとされます。素晴らしい芸術作品に触れ心が感動したとき、人間の魂は一瞬だけ天国に飛びます。絵画や彫刻などは間接芸術であり、音楽こそが直接芸術だと主張したのは、かのヴェートーベンでした。すなわち、芸術とは天国への送魂術だというのです。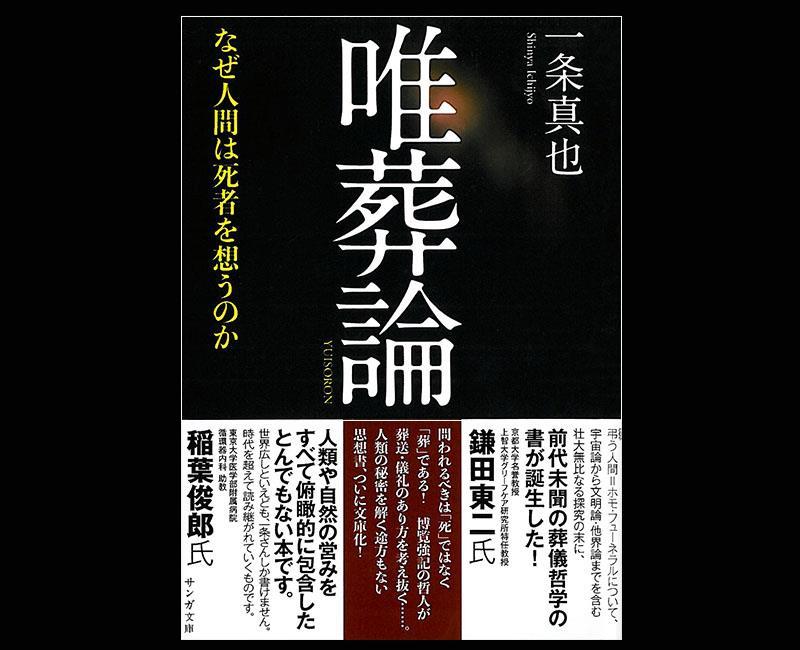
『唯葬論』(サンガ文庫)
拙著『唯葬論』(サンガ文庫)の第7章「芸術論」にも書きましたが、わたしは、葬儀こそは芸術そのものだと考えています。なぜなら葬儀とは、人間の魂を天国に送る「送儀」にほかならないからです。人間の魂を天国に導く芸術の本質そのものであると確信しています。しかし、いわゆるファインアート(造形美術)や音楽を職業とする芸術家たちの多くはその真理を理解することができません。わたしが「葬儀こそは芸術そのもの」という自説を唱えると、露骨に不愉快な顔をする者さえいます。彼らは、冠婚葬祭を世俗主義のきわみのように考えているようですが、まったく考えの浅い連中ですね。
映画「おくりびと」で描かれた納棺師という存在は、真の意味での芸術家です。送儀=葬儀こそが真の直接芸術になりえるのです。「遊び」には芸術本来の意味がありますが、古代の日本には「遊部(あそびべ)」という職業集団がいました。これは天皇の葬儀に携わる人々でした。やはり、「遊び」と「芸術」と「葬儀」は分かちがたく結びついているのです。天皇といえば、5月24日に「羊と鋼の森」を御覧になった天皇陛下は映画の鑑賞後、天皇陛下は監督に「良い映画を観せてもらいました」と述べられたそうです。





