No.514
3月26日、小倉の桜が満開となりました。
この日から公開された映画「ノマドランド」を小倉のシネコンのレイトショーで観ました。これまた、もろにグリーフケアが主題の映画だったので驚きました。なぜか最近は、どんな映画を観てもグリーフケアの映画です。ノマドたちが生活する自然の描写が美しかったです。「月日は百代の過客にして、行きかふ年もまた旅人なり」という芭蕉の『おくのほそ道』の言葉が胸をよぎりました。
ヤフー映画の「解説」には、こう書かれています。
「ジェシカ・ブルーダーのノンフィクション小説を原作に、『ノマド(遊牧民)』と呼ばれる車上生活者の生きざまを描いたロードムービー。金融危機により全てを失いノマドになった女性が、生きる希望を求めて放浪の旅を続ける。オスカー女優フランシス・マクドーマンドが主人公を演じ、『グッドナイト&グッドラック』などのデヴィッド・ストラザーンをはじめ、実際にノマドとして生活する人たちが出演。『ザ・ライダー』などのクロエ・ジャオがメガホンを取り、第77回ベネチア国際映画祭コンペティション部門で金獅子賞を獲得した」
ヤフー映画の「あらすじ」は、以下の通りです。
「アメリカ・ネバダ州に暮らす60代の女性ファーン(フランシス・マクドーマンド)は、リーマンショックによる企業の倒産で住み慣れた家を失ってしまう。彼女はキャンピングカーに荷物を積み込み、車上生活をしながら過酷な季節労働の現場を渡り歩くことを余儀なくされる。現代の『ノマド(遊牧民)』として一日一日を必死に乗り越え、その過程で出会うノマドたちと苦楽を共にし、ファーンは広大な西部をさすらう」
主演は、一条真也の映画館「スリー・ビルボード」で紹介した映画でアカデミー主演女優賞に輝いたフランシス・マクドーマンドですが、彼女の存在感を完全に消し去って、作品あるいは風景に溶け込んだ演技は素晴らしかったです。1957年生まれの彼女は、両親が共にカナダ人。牧師であった父親の都合で各地を転々として育ちます。高校時代にピッツバーグに落ち着き、ウェストバージニア州のベサニー大学で演劇を学びました。さらにイェール大学スクール・オブ・ドラマで学び、その時のルームメイトはホリー・ハンターでした。1980年代初めにホリー・ハンターがコーエン兄弟やサム・ライミと共に暮らしていたことが縁となって、1984年にコーエン兄弟監督の「ブラッド・シンプル」で映画デビューしました。
フランシス・マクドーマンドは、1989年に出演した「ミシシッピー・バーニング」でアカデミー助演女優賞に初ノミネート。1996年の「ファーゴ」および2017年の「スリー・ビルボード」でアカデミー主演女優賞を獲得。主演女優賞複数回受賞は史上13人目の快挙でした。アカデミー賞では、この他に3回助演女優賞にノミネートされています。その後、映画だけでなくテレビや舞台でも活躍。1988年には舞台「欲望という名の電車」に出演し、トニー賞にもノミネートされました。2011年、「Good People」でトニー賞の主演女優賞 演劇部門)を、2015年「オリーヴ・キタリッジ」では、エミー賞の主演女優賞(リミテッドシリーズ・テレビ映画部門)を受賞しています。そんな押しも押されぬ大女優が、「ノマドランド」では車上生活者を演じました。
「ノマド」というと都会を避けて自然の中で生活する人々といった印象があり、ロマンティックなイメージを抱いてしまいますが、ジェシカ・ブルーダー原作の映画化である「ノマドランド」は、そんなロマンとは無縁です。主人公のファーンは61歳の女性ですが、会社の倒産で職を失い、病で夫も亡くしました。生きるために仕方なく、彼女は愛着のあるぽんこつキャラバンに夫との思い出の品を積み、当てのない旅に出ます。生活のため、ところどころで季節労働をします。
彼女が重視した季節労働の1つに、アマゾンの配送センターでの労働がありました。一条真也の新ハートフル・ブログ『amazon』でも紹介したように、アマゾンといえば、世界最先端のIT企業であり、「ビジネスモデル」「キャッシュフロー」「AI技術」「会員サービス」など、ありとあらゆる革命がこの企業には詰まっています。書籍の流通だけではなく、あっという間にさまざまな業界に入り込み、それぞれの大企業を脅かす存在になりました。しかし、その最先端企業の倉庫で働く人々は各地から寄せ集められた困窮した労働者たちであり、悪く言えば「ふきだまり」のような現場の姿がありました。「アマゾンGO」は無人の店舗ですが、これから配送センターもロボット化が進んで無人の職場になるのでしょうか。
マクドーマンド演じるファーンは、ノマドの友人リンダに誘われて、ノマドたちが集まってコミュニケーションを交わすイベント"RTR(Rubber Tramp Rendezvous)"に参加します。最初は不安な表情を浮かべているファーンでしたが、リンダやイベントで出会った新たな友人スワンキーともに交流していく中で、次第に笑顔を見せていきます。アメリカ各地からノマドたちが集まるイベントには大勢のノマドたちが登場します。なんと、プロの俳優は主人公のファーンを演じたマクドーマンドと、デイヴを演じたデヴィッド・ストラザーンのみだそうです。ファーンと親しく会話するリンダ、ギプスをつけて炊き出しに並ぶスワンキー、さらにはイベントの主催者であるボブ・ウェルズをはじめ、全員が一般のノマドたちだそうです。これには驚きました。

奥田知志氏と
ボブ・ウェルズはいわゆるホームレス支援活動家であり、日本でいえば、「隣人愛の実践者」こと奥田知志氏のような存在です。東八幡キリスト教会の牧師で、NPO法人抱樸の理事長でもある奥田氏は、日本におけるホームレス支援活動の第一人者です。これまでに一条真也のハートフル・ブログ「隣人対談」、「無縁社会シンポジウム」、一条真也の新ハートフル・ブログ「茂木健一郎&奥田知志講演会」、天下布礼日記「包摂社会シンポジウム」、一条真也の新ハートフル・ブログ「最期の絆シンポジウム」、天下不礼日記「支え合いの街づくり」、一条真也の新ハートフル・ブログ「荒生田塾講演」などで紹介したとおり、奥田氏とは数多くの対談やシンポジウムでご一緒させていただきました。お互いの活動の場は違っても、ともに有縁社会あるいはハートフル・ソサエティの創造を目指している点では同じであり、同志であると思っています。

奥田氏とは初対面から意気投合!
「ノマドライフ」の主人公ファーンは自分の意志でノマド生活をすることを「ホームレスではなくハウスレス」と表現しましが、これは奥田氏がつねに「ハウスレスとホームレスは違います」と発言されているのと同じです。家をなした人はハウスレスだけれども、絆をなくした人はホームレスだというのです。多くの人々が「絆」を取り戻し、「有縁社会」を再生するのが、わたしの願いです。わたしは、もともと、日本人の「孤独死」と「自殺」を減少させたいと考えてきました。それで、「世界一の高齢化都市」である北九州に全国の独居老人を集めて「高齢者福祉特区」にすべきであるという主張を展開し、そのモデルとしてサンレーグランドホールをオープンさせ、「グランドカルチャー教室」や「むすびの会」をスタートさせました。
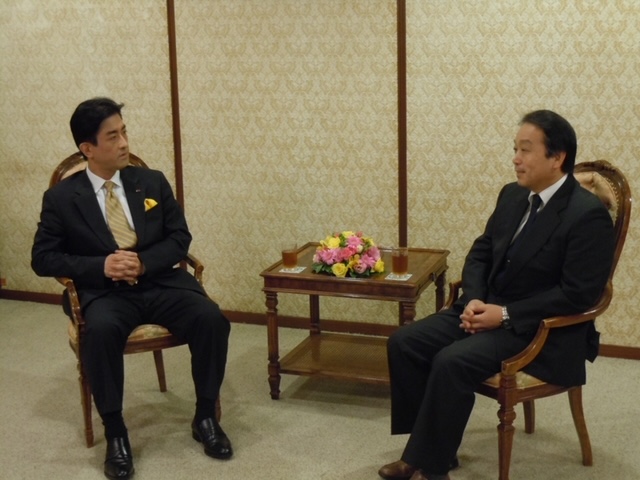
「ケア・シティ」実現に向け、何度も対談しました
また、愛する人を亡くして心神喪失状態にある方々のために「グリーフケア・サポート」の取り組みを進めて、「月あかりの会」や「ムーンギャラリー」を実現してきました。こうなれば、ホームレスや独居老人だけでなく、あらゆる社会的に困っておられる方々、何らかの悩みを抱えている方々に北九州に参集していただき、「とにかく北九州に行けば生きていける」というふうになればいいと思います。すなわち、北九州市を大いなる「社会福祉都市」あるいは「ケア・シティ」にするのです。コロナ時代の社会のテーマは明らかに「相互扶助」であり、それをコンセプトとする互助会の使命とは独居老人やノマドの方々も気軽に立ち寄れる「居場所」づくりだと考えます。そのために、わが社は今後も精力的に取り組んでいくつもりです。

「軒の教会」でグリーフケアを語る
その奥田氏が理事長を務めるNPO法人抱樸が主催する「荒生田塾」で、わたしは講演したことがあります。会場は、生まれ変わったばかりの「軒の教会」でした。建築家の手塚貴晴氏、脳科学者の茂木健一郎氏、政治学者・作家の姜尚中氏といった錚々たる講師陣に続いて出講させていただいたのですが、そのときの講演テーマが「グリーフケアの時代」でした。わたしたちの人生とは喪失の連続であり、それによって多くの悲嘆が生まれます。大震災の被災者の方々は、いくつものものを喪失した、いわば多重喪失者です。家を失い、さまざまな財産を失い、仕事を失い、家族や友人を失いました。しかし、数ある悲嘆の中でも、愛する人の喪失による悲嘆の大きさは特別です。グリーフケアとは、この大きな悲しみを少しでも小さくするためにあるのです。わたしは、そのようなことを話しました。
映画「ノマドライフ」のメインテーマもまさにグリーフケアでした。「アメリカの奥田知志」とでも呼ぶべきボブ・ウェルズは息子を自死で亡くしており、「悲嘆や喪失感を抱いた多くの人々がここに集まってくる」と言います。ファーンもまた、夫を病で亡くし、深い悲嘆と喪失感を抱いています。それが彼女を放浪の旅に駆り立てたのでした。RTRというハウスレスの共同体は、グリーフケアの共同体でもあったのです。ボブ・ウェルズは、「『さよなら』という言葉は『see you again』と言うだろう。そうなんだ、また会えるんだ。永遠の別れじゃないんだ。わたしも、いつかは亡くなった息子に再会できるんだ」と述べるのでした。
 『愛する人を亡くした人へ』(現代書林)
『愛する人を亡くした人へ』(現代書林)
このボブ・ウェルズの言葉は、わたしが初めて書いたグリーフケアの書『愛する人を亡くした人へ』(現代書林)に書いた内容と同じです。考えてみれば、世界中の言語における別れの挨拶に「また会いましょう」という再会の約束が込められています。日本語の「じゃあね」、中国語の「再見」もそうですし、英語の「See you again」もそうです。フランス語やドイツ語やその他の国の言葉でも同様です。これは、どういうことでしょうか。古今東西の人間たちは、つらく、さびしい別れに直面するにあたって、再会の希望をもつことでそれに耐えてきたのかもしれません。でも、こういう見方もできないでしょうか。二度と会えないという本当の別れなど存在せず、必ずまた再会できるということを人類は無意識のうちに知っているのだと。その無意識の底にある真理が、別れの挨拶に再会の約束を重ねさせているのだと。わたしたちは、別れても、必ずまた、愛する人に再会できるのです。
『愛する人を亡くした人へ』には大きな反響がありましたが、同書の中から、CD「また会えるから」が生まれました。この歌の作詞は、わたしが手がけました。YouTubeに動画がアップされています。
そのメッセージとは、「愛する人と死に別れることは人間にとって最大の試練です。しかし、試練の先には再会というご褒美が待っています。けっして、絶望することはありません。けっして、あせる必要もありません。 最後には、また会えるのですから。どうしても寂しくて、悲しくて、辛いときは、どうか夜空の月を見上げて下さい。そこには、あなたの愛する人の面影が浮かんでいるはずです。 愛する人は、あなたとの再会を楽しみに、気長に待ってくれることでしょう」というものです。
ボブ・ウェルズのRTRでは、亡くなったメンバーの葬送のセレモニーを重視しています。この映画では、末期がんに冒された末に亡くなったスワンキーという老女のお別れ会のシーンもあります。キャンプファイヤーのような焚火を囲んだメンバーたちが亡きスワンキーを偲び、彼女が好きだった石を火の中に投げ入れるという儀式です。くだんの奥田氏も葬儀を最重要視されており、ある対談で「私は、支援の初めに私の葬式のときに来てくださいねと言います。お葬式の場というのは、ある意味では残った人たちを支える場です。私が死んだときに、野宿のおじさんたちが何百人か来てくれて、嘘でもいいから『あいつはいい奴やった』と言ってくれと」と発言されていました。奥田氏も、わたしと同じく、葬儀への参列が「縁」と「絆」の核心に通じていることに気づいておられるのです。
「ノマドランド」は、とても美しい映画であったことを強調しておきたいと思います。夜明けとか夕暮れといった「あわい」のシーンが多かったのですが、まるで絵画のような情景で、うっとりとしました。ノマドの人々は必然的に自然と触れ合う機会が多いですが、そこには生物学者のレイチェル・カーソンが「センス・オブ・ワンダー」と呼んだものが育まれ、かつ強められていきます。それは、美しいもの、未知なもの、神秘的なものに目を見張り、人間を超えた存在を認識し、おそれ、驚嘆する感性です。
カーソンは、著書『センス・オブ・ワンダー』で、「鳥の渡り、潮の満ち干、春を待つ固い蕾のなかには、それ自体の美しさと同時に、象徴的な美と神秘が隠されています。自然がくりかえすリフレイン―夜の次に朝がきて、冬が去れば春になるという確かさ―のなかには、限りなく私たちを癒してくれる何かがあるのです」と述べました。まさに、地球の美しさについて深く思いをめぐらせる人は、生命の終わりの瞬間まで、生き生きとした精神力を保ちつづけることができるのであり、ノマドの人々の生き方にはその可能性を感じます。「ノマドランド」は、コロナ時代の生活や人生を考える上でも、とても興味深い映画でした。




