No.1145
10月18日の夜、アメリカ映画「死霊館 最後の儀式」を小倉コロナシネマワールドで観ました。大ヒット・ホラーシリーズの完結編です。大好きなシリーズだったので終わるのはまことに残念ですが、本作もとても面白かった!
ヤフーの「解説」には、こう書かれています。
「実在の心霊研究家であるエドとロレインのウォーレン夫妻が体験した事件に基づく『死霊館』シリーズの完結編。夫妻にとって最後の調査となった1986年のアメリカ・ペンシルベニアでの事件を基に、夫妻の娘を狙う邪悪な悪魔との対決を描く。『死霊館 悪魔のせいなら、無罪。』などのマイケル・チャベスが監督、同シリーズの生みの親であるジェームズ・ワンが脚本・製作を担当。シリーズを通してウォーレン夫妻を演じてきたパトリック・ウィルソンとヴェラ・ファーミガが続投するほか、ミア・トムリンソン、ベン・ハーディらが出演する」
ヤフーの「あらすじ」は、以下の通りです。
「1986年、アメリカ・ペンシルベニアで謎の超常現象が相次ぎ、心霊研究家のエド、ロレイン・ウォーレン夫妻(パトリック・ウィルソン、ヴェラ・ファーミガ)が調査のためにその家を訪ねる。やがて邪悪な悪魔は夫妻の娘で結婚を控えたジュディ(ミア・トムリンソン)に狙いを定め、彼女の将来、そして家族を引き裂こうとする。これまでさまざまな悪霊や悪魔に挑んできた夫妻は、娘を救うためにかつてない脅威に立ち向かう」
いわゆる「死霊館」ユニバースは2013年に脚本家のチャド・ヘイズとケイリー・W・ヘイズが創始したホラー映画のシリーズです。超常現象研究家のエド&ロレイン・ウォーレン夫妻が遭遇した事件を題材にしており、本作を入れてこれまで7作品が発表されています。それらの公開順とストーリー上の時系列は一致していません。時系列順に作品を並べると、1.「死霊館のシスター」(1952年)→2.「死霊館のシスター 呪いの秘密」(1956年)→3.「アナベル 死霊人形の誕生」(1958年)→4.「アナベル 死霊館の人形」(1970年)→5.「死霊館」(1971年)→6.「アナベル 死霊博物館」(1972年)→7.「死霊館 エンフィールド事件」(1977年)→8.「死霊館 悪魔のせいなら、無罪。」(1981年)→9.「死霊館 最後の儀式」(1986年)となります。( )内はストーリー上の年代です。
世界累計興行収入が3000億円を超えるというホラー映画の歴史に燦然と輝く金字塔を打ち立てた「死霊館」シリーズですが、その最後を飾る作品が「死霊館 最後の儀式」です。ついに、シリーズ史上最大の「謎」がすべて明かされます。実在の心霊研究家であるウォ―レン夫妻がこれまで向き合ってきた事件は1000件以上、彼らが挑む最後の事件は、悪魔が複数の死霊を操るという前代未聞のオカルト事件でした。想像を超えた「最後の儀式」が観客を恐怖の底へ誘います。
「死霊館 最後の儀式」の原題は、"The Conjuring:Last Rites"です。Conjuringとは「死霊館」という意味なので、「最後の儀式」がLast Ritesとなります。この「儀式」を意味するRiteという単語から、わたしは一条真也の映画館「ザ・ライト エクソシストの真実」で紹介した2011年のアメリカ映画を連想しました。実話を基に、今なお行われている悪魔祓いとバチカンにおける正式な職業であるエクソシストの全貌に迫った作品です。信仰を見失った若き神学生が悪魔の脅威を目の当たりにし、悪魔祓いを行う司祭エクソシストになるまでを描きます。主演はアンソニー・ホプキンスで、ルーカス・トレヴァント神父を演じました。
エクソシストは、バチカン公認の正式な職業です。バチカンにはエクソシスト養成講座が存在しますし、そこで学んだ者たちが、実際に悪魔祓いの儀式を遂行します。わたしは、もともと一条真也の読書館『バチカン・エクソシスト』で紹介したトレイシー ウイルキンソンの著書を読んでいましたので、この事実を知っていました。前ローマ法王のヨハネ・パウロ2世は、「悪魔は実在する」と断言しました。そして、その在任中に3度にわたってエクソシストとして悪魔祓いの儀式を行っています。中世の遺物であったはずの悪魔祓いの儀式が現代に復活した理由を探ったのが、「LAタイムズ」の女性敏腕記者でローマ支局長を務めたトレイシー・ウイルキンソンでした。この映画には、明らかに彼女をモデルにした女性ジャーナリストが登場します。
「ザ・ライト エクソシストの真実」には、2人のエクソシストが登場します。アンソニー・ホプキンス演じるルーカス神父と、コリン・オドノヒュー演じる神学生のマイケルです。2人とも実在の人物で、ルーカス神父はイタリアで2000回を超える悪魔払いを行い、現在も健在だそうです。また、神学生から神父となったマイケルは、アメリカのシカゴでエクソシストとして活躍しているとか。しかし、この映画の主役はルーカス神父ではなく、若い神学生マイケルです。神も悪魔も、ともにその存在を疑っていたマイケルは、次第に一人前のエクソシストになっていきます。その姿は、ある職業人の成長ストーリーでもあります。そして、マイケルは葬儀業者の息子であり、父親の手伝いをずっと務めてきていました。いきなり映画の冒頭で、遺体安置所で遺体をきれいに整えるシーンが出てきたので、驚きました。マイケルの父は「おくりびと」でしたが、マイケル自身はエクソシストという「はらいびと」になったわけです。
じつは、「おくりびと」と「はらいびと」はとてもよく似た職業です。「ライト(RITE)」という言葉は、「(宗教上の)儀式」という意味です。わたしは、映画「ザ・ライト エクソシストの真実」の原作である一条真也の読書館『ザ・ライト―エクソシストの真実―』で紹介したマット・バグリの著書を読んで、あることを再確認しました。それは、葬儀も悪魔祓いも、ともに「物語の癒し」としての儀式だということです。わたしの一連の著書で書いてきたように、葬儀とは「物語の癒し」です。愛する人を亡くした人の心は不安定に揺れ動いています。大事な人間が消えていくことによって、これからの生活における不安。その人がいた場所がぽっかり空いてしまい、それをどうやって埋めたらよいのかといった不安。動揺して不安を抱え込んでいる心にひとつの「かたち」を与えることが大事であり、ここに、葬儀の最大の意味があります。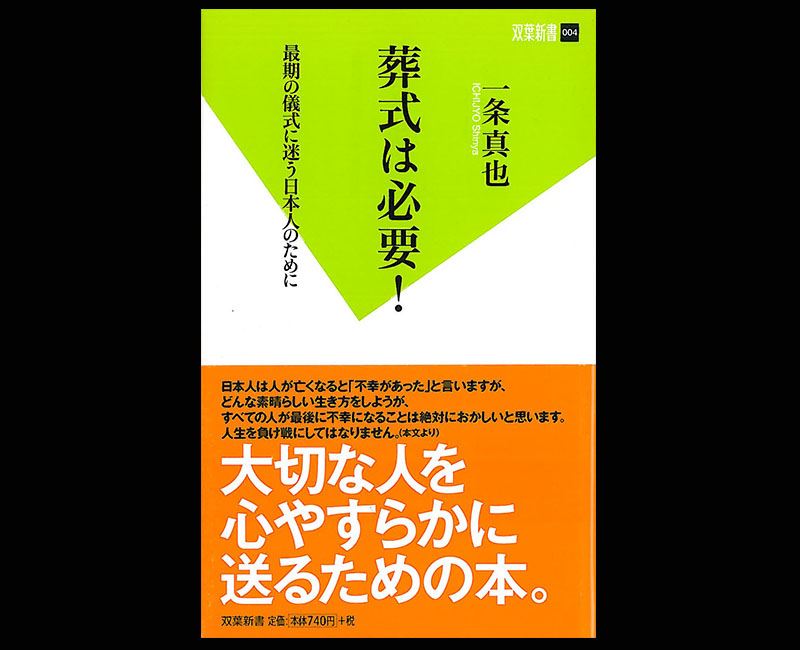
『葬式は必要!』(双葉新書)
この「かたち」はどのようにできているのでしょうか。拙著『葬式は必要!』(双葉新書)に詳しく書きましたが、昔の仏式葬儀を見てもわかるように、死者がこの世から離れていくことをくっきりとした「ドラマ」にして見せることによって、動揺している人間の心に安定を与えます。ドラマによって形が与えられると、心はその形に収まっていき、どんな悲しいことでも乗り越えていけます。つまり、「物語」というものがあれば、人間の心はある程度、安定するものなのです。逆にどんな物語にも収まらないような不安を抱えていると、心いつもグラグラ揺れ動いて、愛する肉親の死をいつまでも引きずっていかなければなりません。死者が遠くへ離れていくことをどうやって演出するかということが、葬儀の重要なポイントです。それをドラマ化して、物語とするために葬式というものはあるのです。
悪魔祓いも同じです。悪魔が実在するのか、実在しないのかは置いておくとしても、悪魔が人間に憑依したものとして、周囲の人間は行動しなければなりません。そして、悪魔と対決し、それを追い払う物語を演じる必要はあります。このへんは一条真也の読書館『スリランカの悪魔祓い』で紹介した文化人類学者の上田紀行氏の著書に詳しいですが、悪魔と対決して追い払ったというドラマを演じることによって、病気だった患者や精神が衰弱しきっていた者が元気になったという実例はたくさんあるのです。葬儀と同じく、悪魔祓いもまた、「物語の癒し」なのです。実際に、物語は人間の「こころ」に対して効力があります。いや、理論の正しさや説得などより、物語こそが「こころ」に対して最大の力を発揮すると言ってもよいでしょう。葬儀や悪魔祓いの儀式という「かたち」には「ちから」があるのです。いっぽうで、「物語の癒し」といった考え方は、文化人類学や民俗学や心理学といった近代的学問の生んだ概念にすぎず、悪魔は実在するし、よって悪魔祓いとしての「エクソシスズム」も実在すると考える人々もいます。
アメリカはプロテスタントの国ですが、プロテスタントの祖であるルターは悪魔の存在を信じていたことで知られています。バチカンにはエクソシストの養成所がありますし、悪魔の存在を認めているという点では、カトリックもプロテスタントも共通しています。わたしは上智大学グリーフケア研究所の客員教授を務めましたが、上智といえば日本におけるカトリックの総本山です。それで神父や修道女の方々にも知り合いが増えたのですが、カトリックの文化の中でもエクソシズム(悪魔祓い)に強い関心を抱いています。なぜなら、エクソシズムとグリーフケアの間には多くの共通点があると考えているからです。エクソシズムは憑依された人間から「魔」を除去することですが、グリーフケアは悲嘆の淵にある人間から「悲」を除去すること。両者とも非常に似た構造を持つ儀式といえるのです。
「魔」も「悲」も放置しておくと、死に至るので危険です。しかし、「魔」や「悲」には対立すべきものがあります。「悪魔」に対立するものは「天使」であり、さらには「神」です。そして、「悲嘆」に対立するものは「感謝」ではないかと思います。神の御名のもとに悪魔が退散するように、死別の悲嘆の中にある人は故人への感謝の念を思い起こせば、少しは心が安らぐのではないでしょうか。「エクソシスト」という言葉を多くの日本人が知ったのは、1973年12月26日にアメリカで、1974年7月13日に日本で公開された映画「エクソシスト」によってです。このホラー映画の歴史に燦然と輝く作品は、少女に憑依した悪魔と神父の戦いを描いたオカルト映画の代表作であり、その後さまざまな派生作品が制作されました。
エクソシストはバチカン公認の正式な職業ですが、「死霊館」の主役であるウォーレン夫妻はバチカンが公認していない民間の心霊研究家にすぎません。当然ながら、教会関係者は夫妻のことを疑いの目で見ます。唯一、夫妻のことを認めて一緒に悪魔祓いをしてきた神父がいたのですが、凶悪で強力なペンシルベニアの悪魔の力で首つり自死をさせられてしまいます。教会の力を頼ることができなくなったウォーレン夫妻ですが、それでも聖書や十字架を手にイエス・キリストの聖なる言葉を悪魔に投げつけます。教会には頼らずとも父なるイエスの力には頼るところがキリスト教の存在感の大きさを感じました。「死霊館」シリーズでは、一貫して描かれるアメリカ社会における教会の役割とか神父の存在といったものが興味深いです。
それにしても、「死霊館 最後の儀式」は、儀式の力の偉大さを痛感させます。RITEは儀式という意味ですが、『RITUAL 人類を幸福に導く「最古の科学」』ディミトリス・クシガラタス著、田中恵里香訳(晶文社)という本を最近読みました。アメリカで大変な話題になった本ですが、冒頭に「儀式は私たちの社会的慣習のほぼすべての根本にある。小槌を振る裁判官や、就任宣誓をする新大統領を思い浮かべてみるだけでもわかるだろう。軍隊でも政府機関でも企業でも、入所式やパレードというかたちで、また忠誠を誓うためにより手間のかかるかたちで儀式が執り行われる。重要な試合でいつも同じソックスを身に着けるスポーツ選手や、高額な賞金がかかるとサイコロにキスしたり幸運のお守りを握りしめたりするギャンブラーもいる。日々の生活のなかで、私たちはみな儀式を行っている。乾杯のときにグラスを掲げ、卒業式に出席し、誕生日会に参加する。儀式は、太古から人々に必要とされ、これから見ていくように人類の文明のなかできわめて重要な役割を果たしてきた」と書かれています。
『儀式論』(弘文堂)
この『RITUAL 人類を幸福に導く「最古の科学」』の内容は、明らかに拙著『儀式論』(弘文堂)のそれに通じています。同書では、わたしは儀式の存在意義について考えました。儀式と聞いて多くの人は、結婚式と葬儀という人生の二大儀礼を思い浮かべるのではないでしょうか。結婚式ならびに葬儀の形式は、国によって、また民族によって著しい差異があります。これは世界各国のセレモニーには、その国で長年培われた宗教的伝統や民族的慣習などが反映しているからです。儀式の根底には「民族的よりどころ」があるのです。日本には、茶の湯・生け花・能・歌舞伎・相撲といった、さまざまな伝統文化があります。それらの根幹にはいずれも「儀式」というものが厳然として存在します。すなわち、儀式なくして文化はありえないのです。儀式とは「文化の核」と言えるでしょう。
「文化の核」などと言うと硬くて面白くない印象を持つかもしれませんが、儀式ほど面白いものはありません。いま、エンターテインメントの世界を席捲しているホラーやファンタジーには必ず儀式が登場します。「スターウォーズ」「DUNE/砂の砂の惑星」などのSFにも儀式は欠かせません。人間には生きていく上で、神話と儀式を必要とします。儀式を描くことによって、その双子である神話が呼び起され、人間の「こころ」の奥深くに届く物語が立ち上がってくるのです。「死霊館」シリーズもまさに儀式を核としたホラー・エンターテインメントです。
「死霊館」シリーズの完結編となる本作では、アナベル人形やスージー人形といった過去のシリーズ作品に登場した人形たちが姿を見せ、恐怖を倍増させてくれました。ウォーレン夫妻は世界中の呪物を集めた博物館を持っていますが、そこに集められているのはやはり人形が多いです。人形とは、人間の「こころ」が宿る「かたち」なのですね。ゆえに多くの呪いの物語を生んできたのでしょう。ブログ「サンクスフェスタ八幡」でも紹介しましたが、わが社では「人形供養祭」を開いています。人形供養祭とは、長年大切にされてきた人形に感謝の気持ちを込めてお別れするための儀式です。神官や僧侶によるお祓い、そして最後はお焚き上げが行われるのが一般的です。多くの神社やお寺で、年に一度など定期的に開催されており、不用になったひな人形や五月人形、ぬいぐるみなどが供養対象です。
ウォーレン夫妻の主苦行である心霊研究家夫妻とは、一言でいって「儀式のプロ」です。夫のエドはカトリック教会が唯一公認した非聖職者の悪魔研究家であり、妻のロレインは透視や霊視能力を持っていると自称していました。「死霊館」シリーズの中で彼らが使う儀式の数々は興味深いものばかりです。アナベル人形やスージー人形といった恐怖の呪物を使いながら、「死霊館」は魔を除去し、人を幸せにする儀式の偉大さを描き続けてきました。その完結編が「最後の儀式」であり、これ以上このシリーズの締めくくりを飾るのにふさわしいタイトルはありません。それにしても、大好きなこのシリーズが終了して、わたしは「死霊館ロス」を感じています。どうか、ホラーの天才ジェームズ・ワンが新シリーズを作ってくれないかな?




