No.747
8月2日の夜、話題のスウェーデン、デンマーク、ノルウェー、フィンランドの北欧合作映画「イノセンツ」をシネプレックス小倉で観ました。サイキックスリラー映画との触れ込みでしたが、これはもう、ずばりホラー映画ですね。終始不気味な雰囲気が漂っていて面白かったです!
ヤフー検索(「ヤフー映画」は「ヤフー検索」に機能統合されてしまいました!)の「解説」には、「第74回カンヌ国際映画祭『ある視点』部門に出品されたスリラー。ノルウェー郊外の団地を舞台に、超能力に目覚めた子供たちが思わぬ事態を引き起こす。メガホンを取るのは『ブラインド 視線のエロス』などのエスキル・フォクト。ラーケル・レノーラ・フレットゥム、アルヴァ・ブリンスモ・ラームスタ、ミナ・ヤスミン・ブレムセット・アシェイムのほか、『マザーズ』などのエレン・ドリト・ピーターセンらが出演する」と書かれています。
ヤフー検索の「あらすじ」は、以下の通りです。
「9歳の少女イーダは、重度の自閉症で言葉を発さない姉アナと共に郊外の団地へ引っ越す。イーダは同じ団地の別棟に住むベンから声を掛けられて森で遊んでいたが、ベンはイーダの握っていた木の棒を凝視しただけで真っ二つに折ってしまう。ベンは念じるだけで物体を動かせる特殊な能力を持っていた。イーダが彼の能力の強さを繰り返し試しているうちに、ベンは他人を自在に操れるまでになるが、次第に鬱々とした感情や思考を増幅させ、過激な行動に走るようになる」
「イノセンツ」はいわゆる北欧ホラーですが、 一条真也の映画館「ミッドサマー」、で紹介した2019年の映画といい、一条真也の映画館「LAMB/ラム」で紹介した2021年の映画といい、北欧ホラーはかなり怖いです。ちなみに、この2本は今や傑作ホラーの製造工場の感があるA24の作品ですね。「ミッドサマー」は一条真也の映画館「ヘレディタリー/継承」で紹介した2018年の長編デビュー作で注目されたアリ・アスターが監督と脚本を務めた異色ミステリーです。スウェーデンの奥地を訪れた大学生たちが遭遇する悪夢を映し出します。「LAMB/ラム」は、アイスランドの人里離れた場所に住む羊飼いの夫婦をめぐるスリラーです。羊から生まれた謎の存在を育てる男女の姿を描き、第74回カンヌ国際映画祭の「ある視点部門」を受賞しました。
「イノセンツ」は、エスキル・フォクト監督自身が告白しているように、大友克洋の名作漫画『童夢』に多大な影響を受けています。ラストシーンなんか、完全に意識していましたね。イノセント(無邪気な)子どもたちが超能力に目覚めて暴走するといった物語は珍しくはありませんが、「イノセント」の舞台であるノルウェーの森と水辺に囲まれた美しい風景の中で描かれると、ひと味違った恐怖を感じてしまいます。ちなみに、主な舞台は団地ですが、『童夢』の舞台は埼玉の団地でした。
『童夢』は、1980年から1981年にかけて4回に分けて雑誌連載された後、1983年に単行本として発行されました。同年、第4回日本SF大賞を受賞しています。大友克洋の代表作の一つで、郊外のマンモス団地で起こる連続不審死事件を巡るモダンホラーです。緻密な描き込みが特徴で、超能力の表現や建物の破壊描写等において、大友の代表作『AKIRA』の原型とも言える作品です。作中に登場する団地は埼玉県川口市の芝園団地を参考に描かれたそうです。1990年代、デヴィッド・リンチ監督で映画化される構想があったそうです。大友は脚本に満足を示し、リンチも企画に前向きでしたが、企画が持ち込まれた米プロパガンダ・フィルムズとリンチの関係が悪化していた時期だったため、制作には至りませんでした。
そんな『童夢』からインスピレーションを得たことをフォクト監督は明かしています。「イノセンツ」を観た日本の観客からも「大友克洋の『童夢』への北欧からの完璧なアンサー」「これは『童夢』実写化と言っても過言ではない」といった声が多数上がっているそうです。フォクトが大友を知ったのは、海外でも根強い人気を誇るアニメーション映画「AKIRA」を観たことがきっかけだとか。大友が描いたマンガの英訳版を探し、1990年代には『童夢』を読んでいたといいます。
フォクトはヨアキム・トリアー監督の北欧ホラー映画「テルマ」(2017年)に関わっていた際に『童夢』を再読。すでに彼には子供がいたことも影響し、大きな衝撃を受けたそうです。そして彼は、「子どもには子どもにしか知り得ない秘密の世界があり、そんな大人にはわからない世界で起こる物語を映画にしてみたい」と考えました。特に『童夢』のクライマックスを参考にしてわけですが、フォクトは「誰にも気付かれないだろうと思ったのですが、日本公開でみんなにバレてしまいますね。日本の皆さんが気に入ってくれることを願います」と語っています。
「イノセンツ」は子ども超能力者同士によるサイキックバトルが展開されますが、その威力は人を殺せるほど破壊力があります。北欧ホラーではありませんが、わたしは、スティーヴン・キングの同名小説をブライアン・デ・パルマ監督が映画化した「キャリー」(1976年)を連想しました。超能力をもった少女キャリーが引き起こす惨劇を描いた青春オカルトホラーです。狂信的な母親のもとで育てられ、学校でも日常的にいじめを受けている少女キャリーは初潮を迎えて動揺しますが、生理現象は汚れの象徴だと母親に罵られます。しかし、その日を境にキャリーは念じることで物を動かせる超能力に目覚めていくのでした。
また、一条真也の映画館「ドクター・スリープ」で紹介した2019年のホラー映画も連想しました。スティーヴン・キングのホラー小説をスタンリー・キューブリック監督がジャック・ニコルソン主演で映画化した「シャイニング」の続編です。一家を襲ったホテルでの恐ろしい出来事から40年後、生き延びた息子ダニーが遭遇する新たな恐怖を描きます。「ドクター・スリープ」も「イノセンツ」もともに超能力者同士のバトルを描いていますが、「キャリー」で描かれる超能力がいわゆる念力(サイコキネシス)なら、「ドクター・スリープ」と「イノセンツ」には相手に恐ろしい幻覚を見せる黒魔術のような能力が描かれます。
『ハートフル・ソサエティ』(三五館)
映画「イノセンツ」について、小説家の乙一は「超能力を真摯に描いた傑作」と絶賛しています。『ハートフル・ソサエティ』(三五館)の「超人化のテクノロジー」に書きましたが、ひと口に超能力といってもさまざまなものがあります。研究者たちは、超能力をPSI(サイ)と総称しており、これは「科学では説明できない、人間が秘める、五感を超える、潜在的、超自然的な能力や現象」を意味する代名詞とされている。そして一般的には、PSI現象は、思念などによって外部環境に影響を及ぼすPK(念力、念動、念写)、透視、テレパシー、霊感などのESP(超感覚的知覚)の2つに分類されます。
スプーン曲げに代表される念力などのPKは、現代社会において、すでに実現されているといってよいでしょう。それは何より、核の存在によります。核はどんなに遠く離れたものでも、この地球ですら一瞬で破壊することのできる強大な念力のテクノロジー化なのです。ちなみに核と並んで20世紀を象徴する道具としての宇宙船は、体外離脱のテクノロジー化です。宇宙船が地球の重力圏から脱出して宇宙空間に出て行くことは、人類の意識が肉体である地球から体外離脱することなのです。その意味で、宇宙体験とは人類にとって臨死体験であり、神秘体験である。核だけではなく、コンピュータもPKを実現してきている。ハッカーと呼ばれる人々は、遠く離れたコンピュータでも自由に、また相手に知られることなく操作することができます。彼らは超大国の軍事までをも思いのままに操ることによって、多くの人々を生かしも殺しもできる恐るべきPK能力者なのです。
PKとともにPSI現象を構成するのがESPです。ESPの諸能力を仏教の用語を使ってわかりやすく表現すると、次のようになります。
1.天眼通・・・・・・透視、千里眼
2.天耳通・・・・・・千里耳(地獄耳)
3.他心通・・・・・・テレパシー
4.宿命通・・・・・・予知、後知
5.神足通・・・・・・テレポート
6.漏尽通・・・・・・悟りの境地
この中でも、ある程度は現在実現しているものがあります。漏尽通は、幽体離脱をテクノロジー化した宇宙船によって獲得することができます。なぜなら、宇宙飛行士の多くは宇宙で神の実在を感じ、悟りのような境地に達したといいます。重力とはあらゆる煩悩の象徴であり、そこから脱出することは悟りへ至ることなのです。ブッダはものすごい苦労をして悟りを開きましたが、無重力の宇宙空間では凡人でも悟りを開けるのかもしれません。
また、神足通は飛行機などによって、宿命通は世界中をケーブルでつながれた1つの世界の市場とした金融テクノロジーをはじめとする情報システムによって、他心通は遠く離れた相手ともコミュニケーションが可能なインターネットや携帯電話の電子メールによって、天眼通や天耳通はテレビやラジオによって、それぞれある程度実現。しかし、それは未来の超人社会から見れば未熟な超能力にすぎません。超情報社会において、人類は万能の超人となるのかもしれません。しかし、それが人間同士が傷つけ合い、殺し合うような暴力的な超能力ではないはずです。新時代の超能力は、仏教の「慈悲」、儒教の「仁」、キリスト教の「隣人愛」などが実体化したものであるべきだと考えます。すなわち、「コンパッション」の能力です。
『コンパッション!』(オリーブの木)
「イノセンツ」に登場する子どもたちは、全員が大きなストレスを抱えています。9歳の少女イーダは、重度の自閉症で言葉を発さない姉アナの世話をすること。ベンは母親から虐待され、学校ではいじめに遭っていること。白斑のある黒人少女アイシャの母は精神を病んでいます。そんな彼らが超能力を身につけたのは尋常でない量のストレスが原因かもしれません。でも、アイシャは互いに離れていてもアナと感情、思考を共有できる不思議な能力を秘めていました。重度の自閉症だったアナは、アイシャによってケアされ、次第に心を開き、言葉を話していきます。わたしは、このシーンに超能力の理想形というものを見た思いがしました。他人同士の心が通じ合い、互いにケアし合う。いわば、究極のテレパシーこそが「心ゆたかな社会」を創造しうるのではないかと思ったのです。万人の心がテレパシーによって繋がれ、互いのグリーフが伝わり合えば、もはや「いじめ」も「ハラスメント」も存在しません。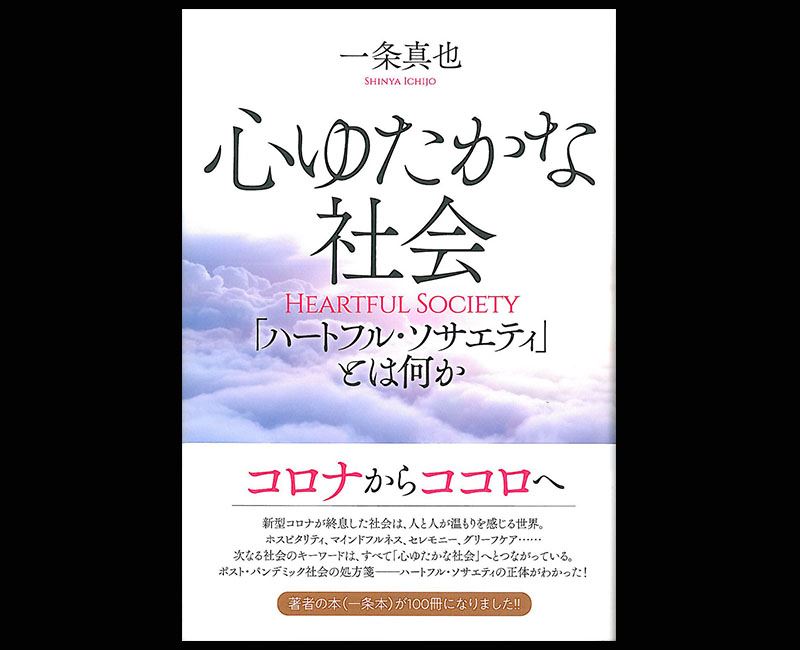
『心ゆたかな社会』(現代書林)




